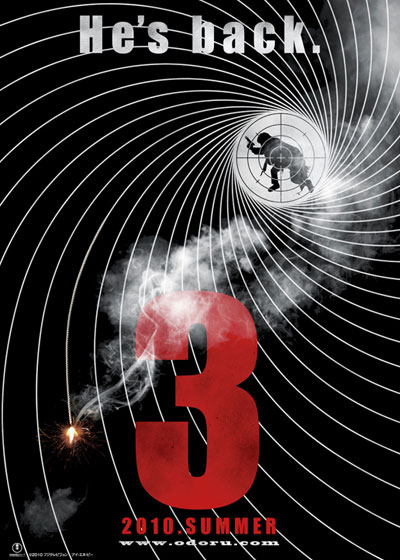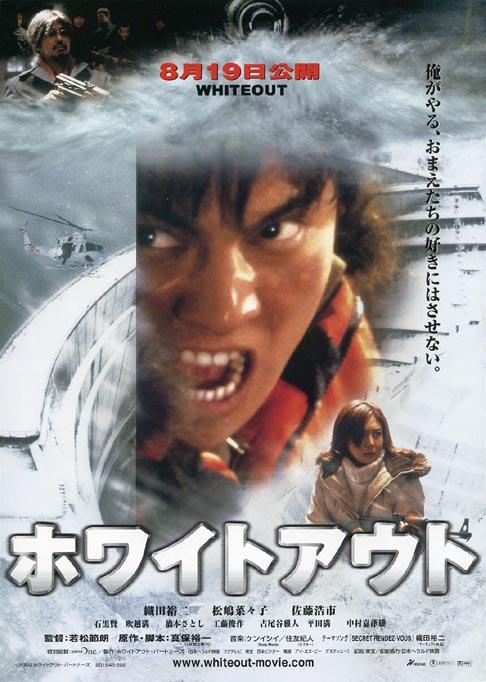仙谷由人官房長官の「日本は個人補償を行うべきだ」発言問題
2010年7月7日の日本外国特派員協会での記者会見で、菅内閣の仙谷由人官房長官が韓国との戦後処理問題について「日本は個人補償を行うべきだ」と発言したことが話題になっています。
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010070700917
産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100707/plc1007072049009-n1.htm
ただでさえカンガンスこと菅直人の消費税増税発言が物議をかもして民主党の支持率低下が危ぶまれる中で、さらに追い討ちをかけるかのごとき今回の発言。
日韓基本条約で最終的な解決とされた戦後処理問題をことさら蒸し返し、国としての補償をさらに追加する行為に、日韓共に一体何の意味と利益があるというのでしょうか?
個人間だろうが国家間だろうが、一度成立した示談の内容は被害者・加害者問わず遵守しなければならないのが普通ですし、もし不服があるのであれば、日韓共にそもそも和解などすべきではなかったでしょう。
しかも、個人補償とやらの支払いで費われるのは日本の国費であり日本国民の税金であり、その負担は当然日本国民にのしかかってくるわけです。
韓国への個人補償など、払う理由も意義もない、まさに無駄金以外の何物でもありませんし、ましてやそのために増税を行うなど、決してあってはならないことです。
そもそも、戦前の朝鮮は日本の一部だったのですから、本来ならば韓国も「当時の日本の一員」として一緒に謝罪と賠償をしなければおかしいはずなのですけどね。
実際、第二次世界大戦前にドイツに併合されていたオーストリアなどは、戦後独立した後、ナチスに協力したことについて「加害者の一員」として謝罪しています。
そのドイツやオーストリアも、謝罪と賠償を行っているのは「ナチスが犯した犯罪」についてのみ、しかもそれでさえ「あれはヒトラーをはじめとするナチス党の人間が勝手にやったこと」として「国家としての責任」を棚上げにしているくらいなのです。
その一方で、戦争終結時に旧満州や朝鮮に置かれていた日本の資産の請求権を全て放棄したのみならず、韓国には援助金名目で当時の金額で8億ドルも支払い、それでもなお謝罪と賠償を求められた挙句に素直に応じてしまう日本。
世界中探しても、これほどまでに「お人好しでカモな国」は他に存在しないでしょうね。
それにしても、今回の件に限らず、民主党の政策は国益および国民の生活向上に何ら寄与しないどころか害にすらなるシロモノが多すぎますね。
外国人にバラまく子ども手当てとやらもその典型例ですし、マニフェストに書かないくせに何が何でも実現させようとしている外国人参政権・夫婦別姓・人権擁護法案なども然り。
政治思想的に共鳴しているであろう田中芳樹のような人間にとっての民主党はまさに理想的な政治団体なのでしょうが、余計な負担を強いられることになる大多数の日本国民にとっての民主党は、究極のアホでなければ生来の犯罪者集団でしかありえませんね。