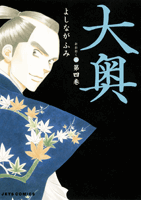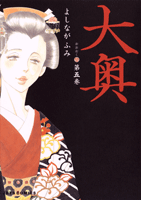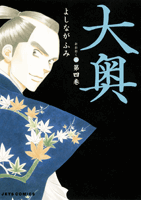
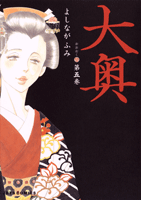
コミック版「大奥」検証考察6回目。
今回の検証テーマは 【「生類憐みの令」をも凌駕する綱吉の暴政】となります。
過去の「大奥」に関する記事はこちら↓
映画「大奥」感想&疑問
実写映画版とコミック版1巻の「大奥」比較検証&感想
コミック版「大奥」検証考察1 【史実に反する「赤面疱瘡」の人口激減】
コミック版「大奥」検証考察2 【徳川分家の存在を黙殺する春日局の専横】
コミック版「大奥」検証考察3 【国内情報が流出する「鎖国」体制の大穴】
コミック版「大奥」検証考察4 【支離滅裂な慣習が満載の男性版「大奥」】
コミック版「大奥」検証考察5 【歴史考証すら蹂躙する一夫多妻制否定論】
徳川3代将軍家光の時代に(作品的にも歴史考証的にも全くもって支離滅裂かつ非論理的ながらも)導入されることになった「大奥」世界における武家の女子相続システム。
本来は変則的かつ緊急避難的に導入されたはずのそのシステムを絶対的なものにしてしまう事件が、徳川5代将軍綱吉の時代に発生します。
その事件の名は、「忠臣蔵」で有名な元禄赤穂事件。
何故この事件が武家の女子相続に関係するかというと、その理由は、事件の発端となった松之大廊下の刀傷事件を引き起こした浅野内匠頭、および吉良邸に討ち入った大石内蔵助をはじめとする赤穂浪士47士中の42人が「史実同様に」男性であったことにあります。
赤穂浪士の吉良邸討ち入り、および町民はおろか幕閣の中にすら赤穂浪士達を擁護する意見があることに激怒した徳川5代将軍綱吉は、感情の赴くままに以下のような発言を行うことになります↓
「これより先、武家において男子を跡目とする旨の届出は全てこれを認めてはならぬ!!
浅野長矩の刀傷然り、赤穂浪士の討ち入り然り…。遠き戦国の血なまぐさい気風を男と共に政から消し去ってしまえ!!」(コミック版「大奥」5巻P195)
この発言が、「大奥」世界の日本における武家の女子相続を決定的なものとし、以後、女子相続が慣習として確立することになってしまうわけです。
……しかし、よくもまあこんな愚劣な発言が「大奥」世界で素直に受け入れられたものだなぁ、と私はむしろそちらの方が疑問に思えてならなかったのですけどね。
件の綱吉の発言には重大な問題がいくつも存在します。
その第一は、そもそも件の発言自体が「討ち入りを行った赤穂浪士達に対する幕府の評定(処分)」の一部として行われていることです。
実際に徒党を組んで他家を襲撃した赤穂浪士達に何らかの処分が下ること自体は、当の赤穂浪士達自身も覚悟していたことでしょうし、家族や旧赤穂藩に所属していた武士達にまで類が及ぶ可能性さえもあるいは承知の上だったかもしれません。
ところが綱吉の発言は、武士階級における全ての男子の存在自体を一方的に断罪している上、吉良邸討ち入りに全く関わっていない武家の相続に対してまで口を出す形になってしまっています。
赤穂浪士達を重罪人として磔獄門にでもすべきだ、と主張している人間でさえ、全く身に覚えのない吉良邸討ち入りの件を口実に、何より大事な自家の相続に余計な口を出されてしまうとなれば、何が何でも赤穂浪士達の処罰に反対する側に回らざるをえないでしょう。
しかも綱吉の時代では、まだ江戸城に参台している武家の男子も少なからず存在していますし、彼らは将軍と顔を合わせる度に「遠き戦国の血なまぐさい気風の象徴」として罵られる可能性まで存在するのですからなおのことです(4巻で綱吉が越後高田藩の継承問題の再裁定を行っている場に参台している武士達は女性と男性が混在している)。
事件とは全く関係のない他人にまで不安を覚えさせ、下手をすれば反感・敵意まで抱かせてしまうような評定を行うなど、論外も良いところではありませんか。
そして件の綱吉の発言があくまでも評定の一部である以上、赤穂浪士達に対する幕府の評定そのものがあまりにも不当なものであると評価されざるをえなくなります。
赤穂浪士達に切腹を命じた綱吉の評定でさえ、作中における町民達からの評判は散々なものでした。
それに加えての綱吉の発言は「赤穂浪士達に対する鬱憤を赤の他人にまで叩きつけている」「男に何か恨みでもあるのか」などといった悪評を追加してしまうことにもなりかねません。
さらに作中における発言当時の綱吉は、ただでさえ「生類憐みの令」をはじめとする失政の数々で評判が地に落ちている有様です。
そんな綱吉の、しかも出発点からして武士・町民問わず多大な反発と敵視が発生するであろう発言に、慣習として万人に受け入れられる余地があるとは到底思えないのですが。
綱吉の発言を現代の事件でたとえると、尖閣諸島沖での中国漁船衝突問題で、海上保安庁の一職員である一色正春がビデオを流出させた件を口実に、当時の民主党政権が「事件の再発を防止するため、海上保安庁そのものを廃止し、その全職員に対し罪を問う」と宣言するようなものです。
尖閣ビデオを流出させた一色正春を民主党首脳部が逮捕・起訴しようとするのに対してさえ、国民からの反発が凄まじかったことを考えれば、ましてや海上保安庁そのものを悪と断罪して廃止するとまで明言しようものなら、当時の民主党政権の支持率はこの時点で一桁台にまでガタ落ちし、さらには大規模な倒閣運動すらも発生しかねなかったでしょう。
しかし、コミック版「大奥」における綱吉は、それと同じ類の発言を、しかも武士階級全体をターゲットにやらかしているわけです。
いかに綱吉の発言が酷いシロモノであるのか、これだけでもお分かり頂けるのではないでしょうか。
第二の問題点は、武家の男子相続の禁止が、徳川3代将軍家光(女性)の遺訓に明らかに反していることです。
太平の世が長く続いた江戸時代ではとにかく事なかれ主義が横行しており、「祖法(昔からの決まりごと)を変えるべからず」という考え方が支配的でした。
そして、春日局の死後、自分が女性であることを正式に公開した家光(女性)は、武家の女子相続について「あくまでもこれは“仮”の措置である」と重臣一同の前で公言しています。
それに真っ向から刃向かっている綱吉の発言は、自分の母親である家光(女性)に対する裏切り行為とすら解釈されかねず、この観点から保守的な武士達からの反感を買うことにもなりかねません。
なまじ徳川家に忠誠を誓っている人間であればあるほど、祖法を蹂躙する発言をやらかしている綱吉には反感を抱かざるをえないところでしょう。
実際、後の徳川6代将軍家宣に仕えた新井白石はまさにそういう考え方の持ち主でしたし、綱吉の死後、家宣はその新井白石の進言を受け、件の綱吉の発言を「生類憐みの令」と共に廃止しています。
第一の理由と併せ、身内を含む武士階級の人間全てを敵に回しかねないという点で、男子相続の禁止令は愚行としか評しようがないのです。
ただ、かくのごとく愚劣な法令であったとしても、それが長い年月の間運用されていれば、江戸時代における「祖法を変えるべからず」の慣習も相まって民衆の間に定着する、ということはあったかもしれません。
徳川5代将軍綱吉の時代における悪政の象徴としてしばしば取り上げられ、20年以上もの間君臨し続けた「生類憐みの令」も近年では見直し評価が行われており、「綱吉の時代にまだ残っていた戦国時代の荒々しい風潮を一掃した」「殺生を禁ずることで治安が改善した」などといった肯定論もあります。
「生類憐みの令」は、長く続けられることによって初めてその効果を民衆の中に浸透させることができる法律だったのであり、だからこそ綱吉もその死の間際に「生類憐みの令だけは世に残してくれ」と遺言した可能性だって考えられるのではないでしょうか。
これから考えれば、妄言の類としか評しようのない綱吉の発言も、「長い年月をかければ」慣習化する可能性も充分にありえたわけですね。
ところがここでも(綱吉にとっては)不幸なことに、綱吉の男子相続を禁止する発言は、それが慣習として根付く時間すら満足に与えられていないのです。
それは綱吉の発言がいつ行われたのかを見ればすぐに分かることです。
元禄赤穂事件における赤穂浪士47士による吉良邸討ち入りが行われたのは、元禄15年12月14日(1703年1月30日)。
それに対し、「生類憐みの令」が廃止されるきっかけとなった綱吉の死去が宝永6年1月10日(1709年2月19日)。
件の綱吉の発言は「生類憐みの令」と一緒に廃止されていますので、武家における男子相続の禁止はわずか6年弱しか続いていなかったことになります。
貞享4年(1687年)から始まったとされる「生類憐みの令」と比較しても3分の1以下の期間しかありません。
ただでさえ綱吉の発言は評価ボロボロで多大な反発やサボタージュを招きかねないようなシロモノだというのに、たったの6年弱でどうやって慣習として定着するというのでしょうか?
しかも、綱吉の発言は「赤穂浪士達に切腹を命じて以降」の男子相続届出を認めないとするものであって、それ以前に認められている男子相続者については当然何の拘束力も発生しません。
たった6年弱では、「赤穂浪士達に切腹を命じる以前に認められていた男子相続者」がそのまま生き残る可能性も少なくないのですから、なおのこと女子相続が慣習として定着する可能性は低くなると言わざるをえないでしょう。
さらに、その時期の綱吉は(江戸時代当時としては)すでに老齢でいつ死ぬかも分からないような状態にあったのですし、綱吉の後継者と目された家宣は「生類憐みの令」にも綱吉の発言にも否定的だったのですから、「犬公方(綱吉の蔑称)が死ぬまで数年程度待てば良い、家宣様が将軍になれば元に戻るから」と考える人間も少なくなかったのではないでしょうか。
綱吉の男子相続禁止令が慣習として根付くには、前提となる条件が根本的に不足しているようにしか思えないのですけど。
前回の検証考察で取り上げた一夫多妻制否定論といい、今回の綱吉の発言といい、「大奥」世界で男女逆転を発生させるための世界設定がここまでズタボロな惨状で、一体どうやって作中のような「大奥」世界が成り立っているのか、私としてはいよいよ深刻な疑問を抱かざるをえないところですね。
男女逆転の過程を描いていると豪語するからには、当然社会システムの変遷およびそれに伴う問題点などについても少しは説得力のある理論や解決方法を提示しているのではないかと期待してもいたのですが……。
さて、次回の検証考察では、「大奥」世界における男性の立場やあり方について考えてみたいと思います。