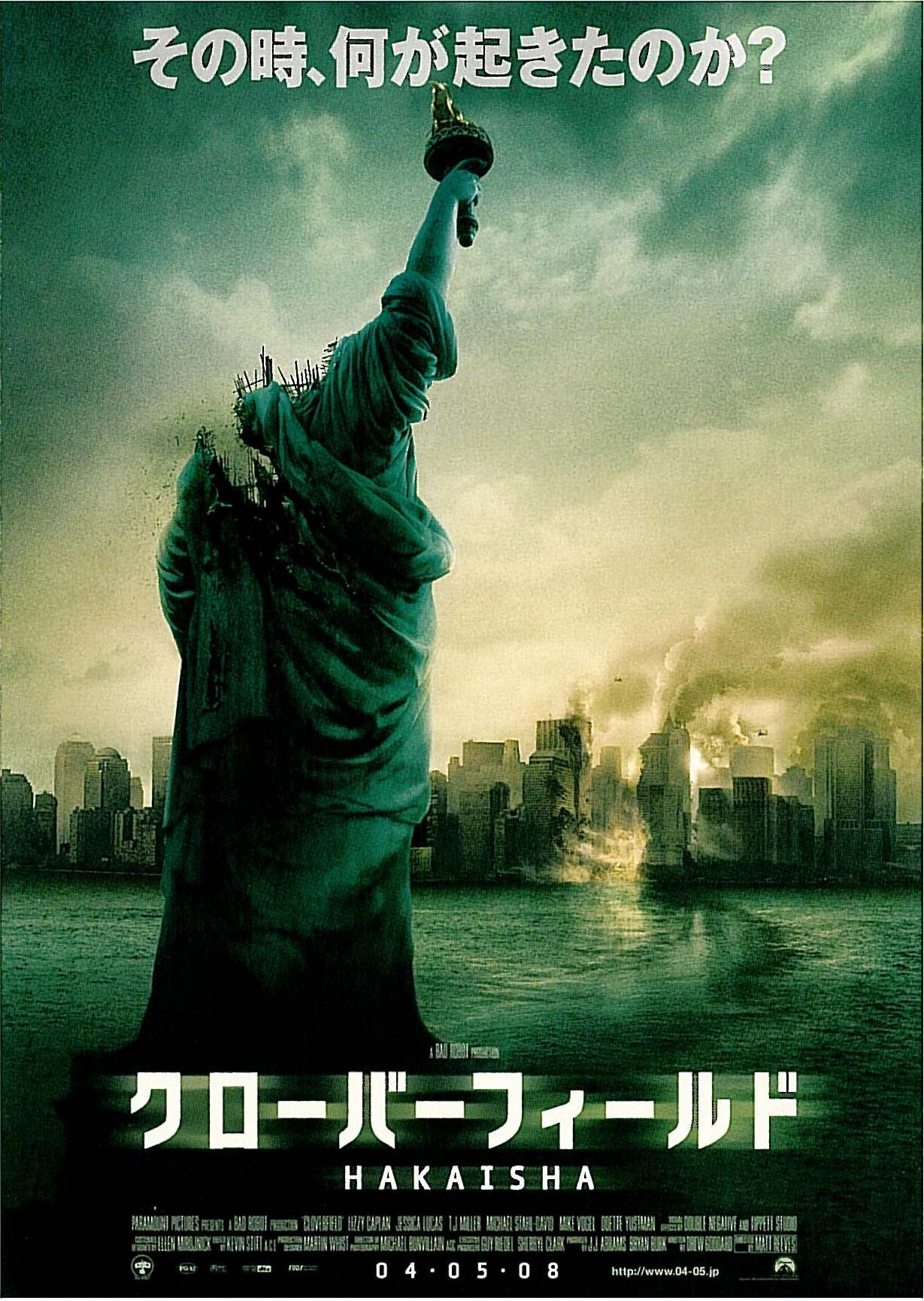映画「日輪の遺産」観に行ってきました。
浅田次郎原作の同名小説を映画化した作品。
この映画、私の地元熊本では熊本市中心部にある熊本シネプレックスでしか上映されていなかったため、そこまで出向いての映画観賞になりました。
この映画のメイン舞台は1945年8月なのですが、物語冒頭は2011年3月から始まります。
まずはアメリカの別荘らしき家でインタビューを受ける日系アメリカ人がクローズアップされますが、彼はその後の物語に繋がるいくつかのキーワードを並べただけでその場ではすぐに出番が終了します。
次に舞台は、同時期の森脇女子学園中等部で行われようとしている卒業式に移ります。
森脇女子学園には、戦前に空襲の犠牲となり死亡したとされる当時の女学生19人と教師1人の名が刻まれた追悼のための石碑がありました。
そこへ、車椅子に乗った老人と年の離れた奥さん、そして彼らの義理の息子(婿養子だったらしい)で構成されている3人がやってきます。
彼らは森脇女子学園に毎年多額の寄付を行うことと引き換えに中等部の卒業式に出席しており、また森脇女子学園で教師職に就いている孫娘と、その孫娘と結婚を前提として付き合っているらしい彼氏に会うことも兼ねて、今回森脇女子学園に足を踏み入れていたようでした。
しかし中等部の卒業式が厳かに執り行なわれていた最中、老人が突然発作を訴えて倒れてしまい、高齢ということもあってかそのまま帰らぬ人となってしまいます。
そして、故人の遺言で密葬が執り行なわれる中、未亡人となった奥さんは、一家の人間と孫娘の彼氏を呼び集め、森脇女子学園の石碑について「あれには本来私の名前も入るはずだった」と前置きした上で、物語の本編となる戦前の話について語り始めるのです。
1945年8月。
日本にとっては敗戦間際の絶望的な状況の中、語り部の奥さんこと金原久枝は、森脇女子学園の前身である森脇女学校の女生徒20名のひとりとして、教師・野口孝吉の指導の下、当時行われていた学徒勤労動員に従事していました。
そんな中、憲兵達が野口孝吉を治安維持法違反で逮捕・連行するという事件が発生します。
1週間後に野口孝吉は無事釈放され女生徒達のところへ戻ってくるのですが、これが伏線となって彼女達の運命が決定づけられます。
一方、日本の帝国陸軍近衛第一師団に所属している真柴司郎少佐は、東部軍経理部所属の小泉重雄主計中尉と共に軍首脳から直々に呼び出され、ある重大な密命を帯びることとなります。
その密命の内容とは、山下奉文によってもたらされたらしい、当時の金額で900億円(現在の金額換算で200兆円)にも及ぶマッカーサーの隠し財産を隠蔽するというもの。
そして、その財産を隠蔽するための勤労要員として、あの森脇女学校の女生徒20名と教師・野口孝吉に白羽の矢が立つことになるわけです。
隠し財産であることは彼女達にも秘密なので、表面的には本土決戦の際の秘密兵器を隠蔽するという口実で作業は進行されていきました。
しかし、4日間におよぶ作業の末、ようやく極秘任務完了の目処が立ってきた頃、軍上層部は真柴司郎少佐に対し、森脇女学校の女生徒と教師に対する内容の命令が送られてきます。
それは、任務の内容が外部に漏れないようにするため、隠蔽作業に従事した森脇女学校の女生徒と教師に死を与えよ、というものだったのです。
映画「日輪の遺産」は、そもそも話の前提条件自体に大きな疑問があります。
一番致命的なのは、そもそも日本側がマッカーサーの隠し財産を隠蔽する必要など、実のところ全くなかったという点です。
マッカーサーの隠し財産を接収した日本政府にしてみれば、その隠し財産をそっくりそのまま戦利品として「公式に」接収し日本の国家予算の一部に組み込み、使い切ってしまえば、何もあんな手の込んだことをしなくてもマッカーサーからの追跡の手を逃れることは簡単に行えてしまいます。
カネはいくらあってもあり過ぎということはないわけですし、戦争にせよ戦後復興にせよ、使用すべき用途はいくらでもあったはずでしょう。
むしろ、死蔵しているも同然の財産を下手に隠蔽し続けることの方が「いつ奪い取られるのか」という不安が常に付き纏う上、隠蔽している間は何の用途にも使えないという点で非合理もいいところです。
一方、マッカーサー側にしてみれば、もしマッカーサーに「自分の命令=国家の意向」レベルの無尽蔵な権力が存在する場合は、奪われた財産の額に相当する賠償金を日本政府に要求してカネを作るという手法を使ってしまえば、わざわざ自分で財産を探す必要それ自体がなくなってしまいます。
マッカーサーは労せずして自分が失った財産をいとも簡単に取り戻すことができるのですし、賠償金を要求された日本政府は、要求されたカネが払えなければ結局自分達の手で隠蔽した隠し財産を自ら掘り起こし、マッカーサーに献上せざるをえなくなるのですから。
そしてここが重要なのですが、実はGHQ時代におけるマッカーサーはそこまでの権力など持ってはいませんでしたし、そもそもあの隠し財産には「アメリカが公式に保有する公のものではない」という大きな弱みがあるのです。
マッカーサーの隠し財産はあくまでも「マッカーサー個人」のものでしかなく、しかも作中におけるマッカーサーの言動を見る限り、マッカーサーはその存在を公にすることすらなく秘密裏に探索を進めています。
アメリカ本国にしてみれば、たかだかマッカーサー個人の隠し財産を補填するだけのために日本政府にカネの要求をするなどという不毛な行為などやりたくもなかったでしょうし、またマッカーサー側からしても、下手にアメリカ本国の公的な意向を背景にしてしまうと、個人的な隠し財産をそっくりそのままアメリカ本国に接収されてしまう危険性があります。
それどころか、隠し財産の半端じゃない金額から考えると何らかの不正が行われている可能性もあるため、下手をすればアメリカ本国から脱税や公金横領等の罪に問われ、財産没収どころか政治生命すら終焉を迎えてしまうリスクもあったりしますよね。
マッカーサーが赴任していた当時のフィリピンは完全な独立国ではなく、マッカーサー本人もアメリカの軍人なのですから。
国家的な背景のない個人的な隠し財産、そこにマッカーサーの致命的な弱みがあるわけです。
また、マッカーサーは物語終盤で偶然にも日本側が隠匿した自身の隠し財産を見つけることに成功します。
ところが、その隠し財産に寄り添うように並んで転がっていた女学生19人の白骨死体と「七生報国」の鉢巻を見てヒステリックに叫びまくった挙句、隠し財産を全く回収することなく「ここは永遠に閉鎖しろ」と部下達に命じてその場を立ち去ってしまうんですよね。
私は何故マッカーサーがそんなことをしなければならないのが、疑問に思えて仕方がありませんでした。
マッカーサー的には、日本人が「簡単に自決する」ことに恐怖を感じてもいたのでしょうが、そういった事例自体を目にするのは別にその時が初めてだったというわけではないでしょう。
作中でも、隠し財産の場所を教えることと引き換えに経済政策についての提言書を受け入れるようマッカーサーに迫った小泉重雄元主計中尉が、拒否の返答を聞くやマッカーサーの眼前でピストル自殺していますし、それ以前にマッカーサーの立場であれば、日本軍の強さや特攻の実態などについて何度も目の当たりにしていたはずです。
それらのことに比べれば、たかだか女学生19人が集団自殺していた程度のことなど「路傍の石ころ」「既に周知の事実」程度の事象に過ぎないわけで、ああまでヒステリックになった挙句、900億円相当の隠し財産を放棄すらしなければならないようなことだったのかと言わざるをえないんですよね。
むしろマッカーサー的には、白骨死体を踏みつけて「バカなジャップ共が意味不明な理由で勝手に死んでくれてせいせいした」とでもふんぞり返り、隠し財産が見つけられたことに素直に欣喜雀躍しても良かったところだったでしょうに。
当時の欧米諸国が当然のように抱いていた人種差別的思想から考えても、マッカーサー個人もかなりの人種差別主義者だったことから言っても、そのように反応する方がはるかに自然だったのではないかと。
たかがあの程度のことであそこまでヒステリックになってしまう(作中の)マッカーサーって、実は軍人や政治家としての適性が著しく欠落しているのではないか、という疑念すら抱いてしまったくらいなのですけどね、私は。
とまあ、政治的な視点で見れば結構色々なツッコミどころがありますが、普通に悲劇物として観賞する分には何の問題もない作品です。
戦時下の絶望的な状況下でアレだけ明るく振る舞い&助け合い、戦争自体に批判的な声すらも上げていた女学生達が、自分達に対する軍からの命令を知った後に自ら率先して集団自決という道を選ぶ結末には驚くべきものがありましたが。
自分達に死を命じる軍の理不尽な命令なんて聞く必要はないし、何も自殺することはなかろうに……とはやはり現代人の考えなのであって、当時の風潮と、何よりも彼女達自身の「純粋さ」からは、あのような結末が導き出されてしまう必然性もあったのでしょうね。
賛否いずれにせよ、色々と考えさせてくれる作品であろうと思います。