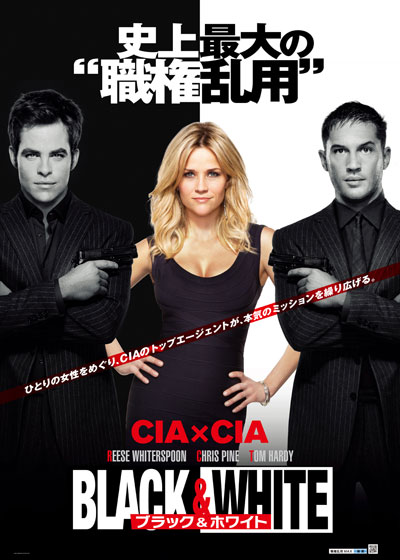今の自分が置かれている現状を招いた責任のほとんど全てが自分自身にあるにもかかわらず、そこから目を逸らして他人を罵り倒し続けるエーリッヒ・ヴァレンシュタイン。
まるでそうしないと生きていられないかのごとく、自分の責任を認めることを何が何でも拒絶するヴァレンシュタインは、必死の形相で格好のスケープゴートを探し始めるのですが、それがまたさらにトンデモ発言を引き出しまくるという悪循環を呈しているんですよね。
素直に自分の非を認めた方が本人もスッキリするでしょうし周囲&読者の人物評価も上がるのに、何故そこまでして「自分は正しく他人が悪い」というスタンスに固執するのか、普通に見れば理解に苦しむものがあります。
まあそれができる人間であれば「キチガイ狂人」と呼ばれることもなく、そもそも私が一連の考察を作ること自体がなかったわけなのですが、一体どのようにすればこんな人物が出来上がるのか、非常に興味をそそられるところです。
「作者氏が意図的に仕込んだ釣りネタ&炎上マーケティング戦略」といった類の作外の「大人の事情」的な要素を除外して物語内の設定に原因を求めるならば、ヴァレンシュタインの(今世だけでなく前世も含めた)家族や育てられた環境に致命的な問題があったということになるのでしょうが、それでもここまで酷いものになるのかなぁ、と。
あるいはもっと単純に、過去に何らかの理由で頭でも強打したショックから、脳の理性や感情を司る機能が回復不能なまでにおかしくなった、という事情も考えられなくはないかもしれませんが……。
今回より、「亡命編」における第6次イゼルローン要塞攻防戦で繰り広げられたヴァレンシュタインのキチガイ言動について検証していきたいと思います。
なお、「亡命編」のストーリーおよび過去の考察については以下のリンク先を参照↓
亡命編 銀河英雄伝説~新たなる潮流(エーリッヒ・ヴァレンシュタイン伝)
http://ncode.syosetu.com/n5722ba/
銀英伝2次創作「亡命編」におけるエーリッヒ・ヴァレンシュタイン考察
https://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-570.html(その1)
https://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-571.html(その2)
https://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-577.html(その3)
https://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-585.html(その4)
https://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-592.html(その5)
https://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-604.html(その6)
ヴァンフリート星域会戦後の自爆発言で、本人が全く自覚することすらなく発生していたヴァレンシュタイン最大の危機は、「神(作者)の介入」によるものなのか、それに関わった登場人物全てが原作ですらありえないレベルの桁外れな無能低能&お人好しぶりを如何なく発揮したがために、誰ひとりとしてその存在に気づくことさえもなくひっそりと終息してしまいました。
自分が致命的な失態を犯したことも、類稀な幸運で命拾いしたこともこれまた当然のごとく知ることがないまま、能天気なヴァレンシュタインは「会戦を勝利に導いた英雄」として称賛され、二階級段階昇進を果たすこととなります。
もちろん、超重度の万年被害妄想狂患者である狂人ヴァレンシュタインがその結果に感謝も満足もするはずなどなく、不平不満を並べ立てるのは当然のお約束なのですが、そのヴァレンシュタインと同様に不満を抱いたのが、ヴァンフリート星域会戦でロクに活躍することができず嘲笑の的となった宇宙艦隊司令長官ラザール・ロボスです。
引き続き第6次イゼルローン要塞攻防戦を指揮することとなったロボスは、その腹いせとばかりにヴァレンシュタインとその一派を自分から引き離し隔離することとなります。
それに対するヴァレンシュタインの反応がこれ↓
http://ncode.syosetu.com/n5722ba/20/
> 頭を切り替えよう、参謀は百人は居るのだが俺が居る部屋には三人しか居ない。俺とサアヤとヤンだ。部屋が狭いわけではない、少なくともあと五十人くらいは入りそうな部屋なのだが三人……。滅入るよな。
>
> 想像はつくだろう。ロボス元帥に追っ払われたわけだ。彼はヴァンフリートで俺達に赤っ恥をかかされたと思っている。バグダッシュは相変わらず世渡り上手なんだな、上手い事ロボスの機嫌を取ったらしい、あの横着者め。グリーンヒル参謀長は俺達のことをとりなそうとしてくれたようだが無駄だった。
>
> 心の狭い男だ、ドジを踏んだのは自分だろう。それなのに他人に当たるとは……。宇宙艦隊司令長官がそれで務まるのかよ。笑って許すぐらいの器量は欲しいもんだ。
>
> まあ、俺も他人の事は言えない。今回はヤンにかなり当り散らした。まあ分かっているんだ、ヤンは反対されると強く押し切れないタイプだって事は。でもな、あそこまで俺を警戒しておいて、それで約束したのに一時間遅れた。おまけに結果は最悪、そのくせ周囲は大勝利だと浮かれている。何処が嬉しいんだ? ぶち切れたくもなる。
>
> しかしね、まあちょっとやりすぎたのは事実だ、反省もしている。おまけにロボスに疎まれて俺と同室なった。ヤンにしてみれば踏んだり蹴ったりだろう。悪いと思っている。
「心の狭い男だ、ドジを踏んだのは自分だろう。それなのに他人に当たるとは……」って、発言した瞬間にブーメランとなって自分自身に跳ね返っているという自覚はないのですかねぇ、ヴァレンシュタインは(笑)。
これまで検証してきたように、ヴァンフリート星域会戦でラインハルトを取り逃した最大の原因は、他ならぬヴァレンシュタイン自身がラインハルトに関する情報提供と補殺目的の提示を怠ったことにあるのですし、1時間遅れた件に関しても、ヴァレンシュタインが救援のための無線通信を乱発したことに問題がある可能性が少なくないわけでしょう。
それにヤンは、なすべきことをやらなかったヴァレンシュタインと違って、すくなくともビュコックに対して補給基地へ向かうように進言すること自体はきちんと行っていたわけですし、それに反対されるのも、ビュコックがその発言を採用するか否かを決定するのも、基本的にヤンの一作戦参謀としての権限ではどうにもならない話です。
そして、そんな場合に強気に出れないヤンの性格も、当時のヤンとビュコックの関係も知悉していながらヤンを配置するよう手配したのも、これまたヴァレンシュタイン本人なのですから、当然その責任もまたヴァレンシュタインに帰するものでしかありません。
この3つの問題がない状態でそれでも同盟軍がしくじったというという想定であれば、ヴァレンシュタインの罵倒にもある程度の正当性が見出せるのでしょうが、現実は全くそうではないのです。
責任論の観点から言えば、ヴァンフリート星域会戦の失敗の責任は、どう少なく見積もっても95%以上、実際のところは限りなく100%近い数値でヴァレンシュタインに帰するものなのですから、その事実を無視してアレだけヤンを責めたのは、ロボスがヴァレンシュタインを遠ざける理由よりもはるかに不当もいいところです。
ヴァレンシュタインが本当に反省すべきなのは「ヤンを責めすぎた」ことではなく、「不当な理由と言いがかりでヤンを責めた」ことそれ自体にあるのです。
「ヤンを責めすぎた」では、「ヤンを責めた」こと自体は正しいことだったと断定しているも同然ですし、それでは結局「本当の原因と問題から目を背けている」以外の何物でもなく、本当の反省とは到底言えたものではないでしょうに。
「ドジを踏んだのは自分だろう。それなのに他人に当たるとは……」とは、むしろ逆にヤンこそがヴァレンシュタインに対して発言すべき台詞であるとしか評しようがないのですが。
そして私がさらにウンザリせずにいられないのは、自分の責任についてここまで無自覚な上に甘過ぎるスタンスを取っているヴァレンシュタインが、他人の過ちを糾弾する際には自分の時と比較にならないほど厳格極まりない態度を示していることです。
「亡命編」ではなく「本編」の話になるのですが、ヴァレンシュタインがラインハルトに愛想を尽かして敵対することを決意した際、こんなことをのたまっていたりするんですよね↓
http://ncode.syosetu.com/n4887n/66/
> 2だが、一番いいのはこれだ。門閥貴族たちを潰せる可能性は一番高い。しかし問題は俺とラインハルトの関係が修復可能とは思えないことだ。向こうは俺にかなり不満を持っているようだし、今回の件で負い目も持っている。いずれその負い目が憎悪に変わらないという保障はどこにも無い。
>
> こっちもいい加減愛想が尽きた。欠点があるのは判っている、人間的に未熟なのもだ。しかし結局のところ原作で得た知識でしかなかった。実際にその未熟さのせいで殺されかけた俺の身にもなって欲しい。おまけに謝罪一つ無い、いや謝罪は無くても大丈夫かの一言ぐらい有ってもいいだろう。
>
> この状態でラインハルトの部下になっても碌な事にはならんだろう。いずれ衝突するのは確実だ。門閥貴族が没落すれば退役してもいいが、そこまで持つだろうか。その前にキルヒアイスのように死なないと誰が言えるだろう?
さて、「亡命編」におけるヴァレンシュタインは、たとえその内実がピント外れ過ぎる反省ではあったにせよ、ヤンに対して「悪かった」とは思っていたわけですよね?
ならば、そのヤンに対して全く謝罪しようともせず、もちろん「大丈夫か」の一言をかけようとすらも考えないヴァレンシュタインは、「本編」における【人間的に未熟な】ラインハルトと一体何が違うというのでしょうか?
しかも実際には、ヤンに対するヴァレンシュタインの罵倒責めは冤罪レベルで不当もいいところだったのですから、本来ヴァレンシュタインは、ヤンに対して謝罪どころか土下座までして許しを請うたり慰謝料を支払ったりしても良いくらいなのです。
ヴァレンシュタインの「未熟」などという言葉では到底収まることのない、幼稚園児以下のワガママと狂人的な電波思考に基づいて、八つ当たりと責任転嫁のターゲットにされたヤンこそ、いい面の皮でしかないでしょう。
自分と他人でここまであからさまに違うダブルスタンダードな態度を、しかもそれを整合するための具体的な理由すらも全く提示することがないからこそ、ヴァレンシュタインは人格的にも全く信用ならないのですが。
原作におけるヤンやラインハルト&キルヒアイスも、すくなくとも狂人ヴァレンシュタインなどよりは、自分に対してそれなりに厳しい態度を取っていたと思うのですけどねぇ(-_-;;)。
ヴァレンシュタインが同じく罵りまくっているロボスやフォークなどは、まさに「自分には甘いくせに他人にはとてつもなく厳しい性格」な人間であるが故に周囲&読者から白眼視されているのですし、一般的に見てさえもそんな性格の人間なんて、「人間的な未熟さを露呈している」どころか「傍迷惑なキチガイ狂人」以外の何物でもないでしょうに。
この期に及んでも、とことんまでに自分自身のことを自己客観視できない人間なのですね、ヴァレンシュタインは。
ところで、これまでの考察でも何度か書いているのですが、私は以前から「ヴァレンシュタインは何故『自身が転生者である事実』を徹底的にひた隠しにするのか?」という疑問をずっと抱き続けています。
あまりにも秘密主義に徹しすぎるので、「実はこいつは元々人間不信的な精神的障害か疾患でも抱え込んでいて、自分以外の他者を誰ひとりとして信じることができない体質なのではないか?」とすら考えたくらいでしたし。
これまでは「本編」も含めてヴァレンシュタインが転生の問題を秘密にする件について語る描写が全くなかったため、その理由については推測の域を出ることがなかったのですが、「亡命編」の22話でついにヴァレンシュタインが自身の転生問題について語っている場面が登場しました。
で、その部分が以下のようなモノローグとして表現されているのですが…↓
http://ncode.syosetu.com/n5722ba/22/
> ラインハルトが皇帝になれるか、宇宙を統一できるかだが、難しいんだよな。此処での足踏みは大きい。それに次の戦いでミュッケンベルガーがコケるとさらに帝国は混乱するだろう。頭が痛いよ……。俺、何やってるんだろう……。
>
> おまけにヤンもサアヤも何かにつけて俺を胡散臭そうな眼で見る。何でそんな事を知っている? お前は何者だ? 口には出さないけどな、分かるんだよ……。しょうがないだろう、転生者なんだから……。
>
> せっかく教えてやっても感謝される事なんて無い。縁起の悪い事を言うやつは歓迎されない。そのうちカサンドラのようになるかもしれない。疎まれて殺されるか……。ヴァンフリートで死んでれば良かったか……。そうなればラインハルトが皇帝になって宇宙を統一した。その方がましだったな……。人類にとっても俺にとっても。
>
> いっそ転生者だと言ってみるか……。そんな事言ったって誰も信じないよな。八方塞だ……。俺、何やってんだろう……。段々馬鹿らしくなって来た。具合悪いって言って早退するか?
……何ですか、この支離滅裂な論理は?
「本編」でも「亡命編」でも、持ち前の原作知識とやらを盛大に振る舞い、周囲から称賛と恐怖混じりの注目を浴びると共に多大な恩恵まで享受していたのは、一体どこの誰だったというのでしょうか?
ヴァレンシュタインと彼が持つ原作知識のために、「本編」および「亡命編」のラインハルト&キルヒアイスは本来被るはずもない災厄と破滅の運命を押しつけられたというのに、何とまあ被害者意識に満ちた発想であることか。
そこまで転生者としての自分の立場と原作知識が疎ましかったのであれば、そもそも原作知識など封印して何の才幹も披露することなく、また原作に関わる政治や軍事に関与することもなく、ごく普通の一般庶民としての人生を送っていれば良かったでしょうに。
ヴァレンシュタインが原作知識を駆使して原作の歴史を変えたのは、他の誰でもない自分のためでしょう。
誰に強制されたわけでもなく自分の意思で、原作知識を当然の権利であるかのごとく使い倒して(客観的に見れば)非常に恵まれた地位と立場にあるにもかかわらず、その原作知識に対してすら感謝するどころか不満さえ抱くヴァレンシュタイン。
こんな愚劣な思考で動いているのであれば、ヴァレンシュタインが同盟に亡命した際に謝意ではなく不平満々な態度を示していたのも納得ですね。
原作知識という「絶対的な世界の理」を持つ自分が他者と比べてどれだけ恵まれているのか、ヴァレンシュタインはもう少し思いを致し、その境遇に感謝すべきなのではないのかとすら思えてならないのですが。
そしてさらに問題なのは、一方では原作の歴史を変えるレベルで原作知識を使うことに躊躇がないくせに、他方では「転生者であるという事実」をありとあらゆる人間から隠すという、ヴァレンシュタインの非常に中途半端なスタンスにあります。
「本編」でも「亡命編」でも、ヴァレンシュタインは原作知識に基づいた的確な予測と判断で周囲を驚愕させ、その見識を称賛される一方、なまじ才幹があるラインハルトやキルヒアイス、ヤンなどから恐怖と警戒の目で見られるという問題を抱え込んでいました。
その恐怖の根源は、ヴァレンシュタインの神がかった(ように見える)手腕や才覚がどこから来るものであるのか理解できず、得体のしれない存在を見る目でヴァレンシュタインを評価せざるをえなかったことに尽きます。
「こいつは不気味だ」「何を考えているのか分からない」と見做される人間に恐怖と警戒心を抱くのは、動物の本能的に見ても至極当然のことなのですから。
しかし、もしヴァレンシュタインが自身の秘密を明かし、その原作知識を売り込みにかかっていれば、彼らの恐怖と警戒心を解消させると共に強固な信頼関係を獲得することも充分に可能だったのです。
もちろん、最初は当然のごとく「お前は何を言っているんだ?」という目で見られるかもしれませんが、原作知識を持つヴァレンシュタインがその存在を立証するのは極めて容易なことです。
実際、作中でもヴァレンシュタインの「預言」や「奇跡」は実地で何度も立証されているわけですしね。
そして一方、転生および原作知識の秘密は、何も全ての人間に共有させる必要もありません。
ヴァレンシュタインが自分の人生を託すべきごく限られた人間、「本編」ではラインハルト&キルヒアイス、「亡命編」ではシトレとヤン辺りにのみ、「信頼の証」「自分達だけの秘密」として教えれば良いのです。
原作知識から考えても、彼らならばヴァレンシュタインの秘密を「非科学的だ!」の一言で頭ごなしにイキナリ否定することはないでしょうし、立場的にも才覚の面で見ても、すくなくともヴァレンシュタイン単独の場合よりもはるかに有効に原作知識を活用することが可能だったでしょう。
何よりも、そういった有益な知識を供給してくれるヴァレンシュタインに、大きな利用価値を確実に見出してくれるはずですし、上手くいけばヴァレンシュタインが永遠に持つことのないであろう「恩義」というものも感じてくれたかもしれないのです。
何でもかんでも被害妄想を抱き、「恩は踏み倒すもの」「恩には仇で報いるべき」という信念でも持っているとしか思えないヴァレンシュタインには到底理解できない概念なのでしょうが、すくなくとも銀英伝世界ではヴァレンシュタインと違って「恩には感謝する」人間の方が数的には多いものでしてね(爆)。
自身の秘密をヴァレンシュタインが「限られた他者」に打ち明けるだけで、これだけの恩恵をヴァレンシュタインは得ることができたのです。
一方、そういった選択肢を取らなかったことで、ヴァレンシュタインがどれほどまでの不利益を被ってきたのかは、「本編」および「亡命編」の惨状を見れば一目瞭然でしょう。
「本編」でヴァレンシュタインがラインハルト&キルヒアイスと決別してしまったのも、「亡命編」でヴァレンシュタインが周囲、特にヤンから警戒されるようになったのも、突き詰めれば全てヴァレンシュタインの秘密主義が最大の元凶です。
そしてさらに「亡命編」では、ラインハルトの情報を同盟軍首脳部に事前に提供しなかったがために、ヴァレンシュタインが悔いても悔やみきれない「ヴァンフリート星域会戦におけるラインハルト取り逃がし」という結果を招くことになったわけでしょう。
これにしても、ヴァレンシュタインが自身の秘密とラインハルトによってもたらされる未来図を提示して殲滅を促していれば、目的が達成できた公算はかなり高いものになったはずなのですが。
「縁起の悪い事を言うやつは歓迎されない」「そんな事言ったって誰も信じない」というのは、転生という事実を目の当たりにしながら「科学教」という名の新興宗教の教義に呪縛されているヴァレンシュタインの、それこそ非合理的かつ「非科学的な」思い込みに過ぎないのです。
そもそも「非科学的」というのであれば、先のヴァンフリート星域会戦におけるヴァレンシュタインの自爆発言の数々に、作中の登場人物の誰ひとりとして何の疑問も疑念も抱かず、その重要性に気づきすらもしなかったことこそが、奇妙奇天烈な超怪奇現象以外の何物でもないのですし(笑)。
あの時点では誰も知りえない原作知識の話をあれだけ披露しても裏付けひとつ必要なく素直に信じてもらえるのであれば、「ヴァレンシュタインが転生者である」という突拍子もない秘密の告白だってすぐさま信じてもらえるでしょうよ(爆)。
正直、作中の描写から考えてもあまりにも無理のあり過ぎる論理としか評しようがなく、「転生の秘密を隠さなければならない理由」としては全く成り立っていないですね、ヴァレンシュタインの説明は。
それにしても、「転生」などという超常現象を目の当たりにしてさえ、「科学」の論理に束縛されて「非常識な【常識的判断】」をしてしまうというヴァレンシュタインの滑稽極まりない光景は、同じ田中作品である創竜伝や薬師寺シリーズで幾度も繰り返された「オカルトを否定しながらオカルトに依存する」あの構図をついつい想起してしまうものがありますね。
「科学」というのは事実を否定する学問などではないのですし、いくら科学的に説明不能な超常現象であっても、それが目の前に事実として現れた時、道を譲るべきは「科学」の方なのであって、「事実」を「科学」に合わせるなど本末転倒もはなはだしいのですが。
科学で本当に重要なのは「結論」そのものではなく「結論までに至る検証過程」なのであって、その過程を経て得られた「結論」だけを取り出し、ある種の権威として盲目的に信奉し他者を攻撃する武器として振り回すがごとき行為は、中世ヨーロッパの魔女狩りと同じシロモノでしかなく、むしろ科学を貶めるものですらあるでしょうに。
田中芳樹もそうなのでしょうが、ヴァレンシュタインもまた、その手の「科学の宗教的教義」の信奉者であると言えるのではないかと
「転生」などという一見不可解な現象を、証明の過程を経て他者を納得・信用させる、実はこれも立派な「科学」の手法なのですけどね。
まあ、科学の手法というのは相当なまでの根気と忍耐を必要とするものですから「それと全く無縁な人生を歩んできた狂人ヴァレンシュタインに果たして実践できるものなのか?」と問われると、私としては無条件で否定的な回答を返さざるをえないところではあるのですが(苦笑)。
次回も引き続き、第6次イゼルローン要塞攻防戦におけるヴァレンシュタインの言動について検証を続ける予定です。