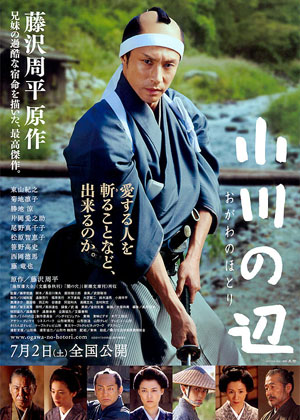映画「アイ・アム・ナンバー4」感想
映画「アイ・アム・ナンバー4」観に行ってきました。
侵略者モガドリアンに滅ぼされた惑星ロリアンの選ばれし生き残り達が、覚醒した特殊能力を駆使して戦うアクション物。
ジェームズ・フライとジョビー・ヒューズによる同名のSF小説を原作としている作品です。
なお、今回初めて映画のフリーパスポートなるものを獲得し、これから1ヶ月間、映画が無料で観覧できるようになりました(^^)。
予定では今作も含めて総計6本の新作映画を無料で観賞する予定です。
物語は、ケニアの奥地にある山小屋で自然に溶け込むかのようにひっそりと生活していたナンバー3とその守護者(ガーディアン)が、深夜に突如モガドリアン一派に襲撃され殺されてしまうところから始まります。
ナンバー3を殺害したモガドリアン達は、ナンバー3が所持していたペンダントのようなものを奪い取り、いかにも目的を達成したかのごとき笑いを浮かべます。
ちょうどその頃、アメリカのフロリダ州マイアミにある海岸で友人達とのパーティーに参加していたナンバー4は、突如足に激痛を覚え、ナンバー3が殺される幻影を見ることになります。
それと共に、激痛の元である足には光と共に謎の紋様が浮かび上がり、その様子をパーティーに集っていた人々に目撃されることになります。
後で判明したことですが、その様子はしっかり動画が撮られており、さらにその動画はご丁寧にもYouTubeにアップデートまでされていました。
ナンバー4の守護者で同時に保護者でもあるヘンリーは身の危険を感じ、家の中にある自分達の身分を証明するものを一切合財処分した後、ナンバー4と共にオハイオ州のパラダイスという町に移り住みます。
その後、ナンバー4がいたマイアミの家は謎の女(後でナンバー6と判明)に焼き払われ、やや遅れてモガドリアン達にも物色されていたので、ヘンリーの判断は間違っていなかったわけです。
しかしそうとは知らず、度重なる逃亡生活にいいかげん忍耐の限界に来ていたナンバー4は、息を潜めた生活を命じるヘンリーに反発し、地元の学校に通う手続きを独断で行ってしまいます。
通い始めた学校でジョン・スミスという偽名を名乗り始めたナンバー4は、カメラを愛する美少女サラ・ハートと、彼女の元カレで学校の競技選手であるマーク・ジェームズに陰湿なイジメを受けている科学&UFOオタクのサム・グッドに出会います。
次第に2人と打ち解け、友好的な関係を構築していくナンバー4ですが、そんなある日、授業を受けている最中、奇妙な幻影と共に突如両手が熱く光り出す事態が発生します。
異変を察知したヘンリーから、それが自分の持つ遺産(レガシー)こと特殊能力の覚醒であることを知らされるナンバー4。
能力が制御できるようになるまで休校するようにヘンリーから命令されるナンバー4ですが、ナンバー4は特殊能力を駆使して家を脱走。
町に繰り出したナンバー4は、そこで偶然サラ・ハートと出会い、彼女の自宅に招かれ、そこで身の上話をしている内に彼女に惹かれるようになります。
しかし、元カレでサラ・ハートをストーカーのごとく付け狙っているマーク・ジェームズが、彼女の家から出て行くナンバー4を目撃。
彼は翌日からナンバー4に対するイジメを始めるようになり、さらにはパラダイスの春の祭典であるカーニバルでサラ・ハートとデートをしていたナンバー4に集団で襲い掛かります。
しかし彼らは能力に覚醒したナンバー4の敵ではなく、あっさりと逆襲された挙句、マーク・ジェームズは右手を折られかけます。
結果として警察沙汰にまでなり、さらには前述のマイアミでの動画がYouTubeにアップデートされた事実までもが発覚するに及んで、ヘンリーは再び町を捨てて逃亡することをナンバー4に勧めます。
しかし、ナンバー4はサラ・ハートに恋をしていることを告げ、その提案を拒否。
そういうしている内に、ついにナンバー4の居所を特定したモガドリアン達がパラダイスに到着し、陰で蠢動し始めることになるのですが…。
映画「アイ・アム・ナンバー4」は、全体的に見ると明らかに「シリーズ作品の第1作目」的な構成になっていますね。
冒頭に出てきたペンダントや、物語後半に登場する謎の箱については、一体何なのかすら最後まで全く明らかになっていませんし、最後のシーンも「殺された3人とナンバー4&6以外の残り4人の仲間達を探す旅に出る」描写で終わっています。
そもそも、モガドリアン達は惑星ロリアンを滅ぼした前歴もあるわけですし、地球についても破壊する意思を明らかにしているのですから、チマチマと9人のナンバーズ達を殺していかずとも、地球を丸ごと破壊するなり全世界に絨毯爆撃を敢行するなりして地球もろともナンバーズ達を始末してしまった方が、はるかに効率も良いのではないかとすら考えてしまったのですが。
もっとも、モガドリアン達はナンバーズ達が持っているペンダントに何故か固執しているようでしたし、物語終盤でナンバー4を追い詰めた際にも、ペンダントを握り締めながら「これでこの星を破壊できる」的な発言を行っていましたから、ペンダントに本来の力を封じられているみたいな設定でもあるのかもしれないのですが。
全く何の説明もなかったこの辺りの謎の数々は、続編によって明らかにされていくことになるのではないかと。
作中におけるナンバー4と、後半に正体が明らかになるナンバー6は、それぞれの特殊能力を駆使してモガドリアン達とバトルを繰り広げていきます。
ただ、ナンバー6の特殊能力は超加速タイプのテレポートと耐火能力がメインで比較的分かりやすいのに対し、主人公ナンバー4のそれにはやたらと多機能性が付加されていて能力の方向性がまるで特定できないですね。
敵の光線銃を弾くシールドの役割をしたかと思えば、熱を持ったレーザービームのような使い方ができたり、さらにはナンバー6の体力を回復するヒーリング的な能力まで披露されたりしていました。
屋根から地表に落下するサラ・ハートを空中で止めるというサイコキネシス的な描写もありましたし、一体どれだけ使用用途が広いのかと。
今後続編が出た際には、さらに別の能力が追加付与される可能性もありえますね。
また、モガドリアン達が黒いトラックに引き連れていた怪物と、ナンバー4がパラダイスの町に引っ越してきた際に拾った犬に化けていた守護獣のキマイラとの戦いはかなり笑わせてもらいました。
学校内を舞台に繰り広げられたこの両者の対決は、破壊されたトイレだかシャワールームだかで決着を迎えることになるのですが、この手の映画のお約束よろしく、最初はモガドリアンの怪物の方がキマイラを圧倒するんですよね。
そしてキマイラに重傷を負わせて壁に叩き付け、さあいよいよトドメとばかりに怪物がキマイラに向けて突撃を敢行したその直後、何と怪物は水で濡れたタイルに足を滑らせてすっ転んでしまい、キマイラの眼前で仰向け状態になってしまうのです。
当然キマイラ側がこんなチャンスを逃すわけもなく、怪物は仰向けで晒された喉元を噛み砕かれてあっさり死亡。
私も色々なハリウッド映画を観てきましたが、こんな「自滅」「自爆」以外の何物でもない爆笑ものの退場を余儀なくされたモンスターはあまり記憶にありませんね。
私はてっきり、どこかから援軍が来るか、キマイラが起死回生の奇策でもって何らかのカウンターを繰り出してくるという、これまたお決まりのパターンばかり考えていたので、良くも悪くも意表を突いた描写になりました。
いかにも「凄まじく凶暴であるが故に強そうなモンスター」として描写されていただけに、その無様な死に様はあまりにも滑稽としか言いようがなかったですね。
あと、ナンバー4とサム・グッドに対するイジメや嫌がらせに躍起になっていたマーク・ジェームズが、物語の最後に元気な姿で再登場していたのには少々驚かされました。
彼って、物語後半でモガドリアン達に捕まった挙句、モガドリアン一派のひとりにブン投げられて学校校舎2階?の窓に叩きつけられる描写があるんですよね。
この手の小人にハリウッド映画は躊躇なく「死」という末路をあてがうのが常ですし、「ああ、あいつは死んだね」とすっかり思い込んでいたのですが。
最後では隔意があったはずのナンバー4達にいつのまにか協力的になっていましたし、マーク・ジェームズに一体何があったのかと、この辺りは少々疑問に思ったものでした。
アクションシーンはスピーディーで迫力もあり、またストーリーもある意味「安心して観れる」作品と言えます。
ただ前述のように、作中の設定には最後まで全く明らかにならない謎の部分が結構多いので、作品単独ではなく「シリーズ物1作目」と割り切って観た方が良いでしょうね。