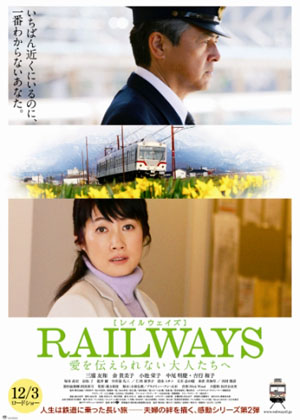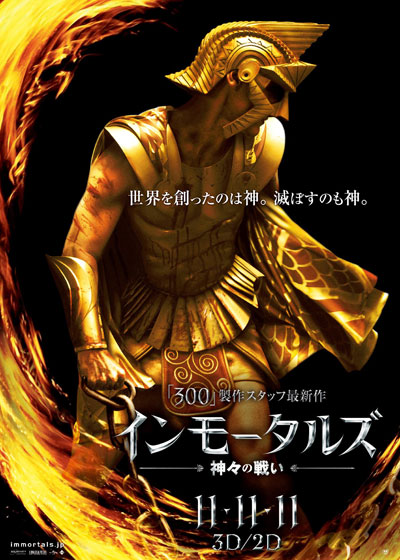私の全く知らないところで、私のハンドルネームを騙って他所のブログを荒らす「騙り投稿」が行われるという事件がいつの間にか発生していました↓
白き焔BLOG
http://blog.goo.ne.jp/masoho-zero
よしながふみ論+「大奥」レビュウ
http://blog.goo.ne.jp/masoho-zero/e/b9a23fcf2c8958f2a34717b104cce818(魚拓)
2005年10月にアップされたというこの記事に「騙り投稿」が行われたのは2011年11月。
しかし、そもそも私はこのブログの存在自体、12月に入り今回の騒ぎが発覚するまで全く認知しておらず、「騙り投稿」が行われた11月時点で私が「白き焔BLOG」に投稿を行うのは不可能なんですよね。
HNこそ「冒険風ライダー」と銘打ってありますが、上記記事で11月に行われた以下の投稿↓
Unknown (冒険風ライダー)
2011-11-22 17:26:52
Unknown (冒険風ライダー)
2011-11-22 22:25:20
Unknown (冒険風ライダー)
2011-11-23 22:23:44
↑については私のものでは断じてないことを、この場を借りてまずは明言させて頂きます。
タナウツでの「騙り投稿」事件と言えば、12年以上も前に当時の「あめぞう」で、私も含めたタナウツ常連複数名のHNを騙った投稿が行われた事例があります。
「騙り投稿」なんて使い古された上に対策も作られ続けてきた「古い」手法ですし、今どき「騙り投稿」なんてずいぶんと古臭くて珍しい事件だよなぁ、というのが、騒ぎを知った私が最初に抱いた感想でしたね(苦笑)。
投稿内容を見ても、私が過去に場外乱闘掲示板その他で全くの別件から書いた投稿文をコピペ改竄しているだけでしかありませんし。
さて、この「騙り投稿」をした人物の正体は一体誰なのか?
まず一番の手がかりは、問題の「騙り投稿」が、よしながふみ原作「大奥」について過去に私がブログに書いた「コミック版「大奥」検証考察」シリーズのひとつを紹介していること。
ここで「騙り投稿」は以下のURLを紹介しているのですが↓
https://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-293.html
しかし、実は上記URLの記事は、「大奥」絡みの記事としては最新のものではないんですよね。
2011年12月7日時点における「大奥」関連の最新記事は以下のURLになります↓
https://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-313.html
「大奥」を扱った各記事には、それまでに書いていた過去の関連記事へのリンクも掲載しており、もし私が「大奥」関連の記事を他者の掲示板なりブログなりで紹介するのであれば、過去記事の関連リンクが全て掲載されている最新の記事を紹介するでしょう。
何故関連リンクが全て揃っていない(リンク数が)中途半端な記事を紹介しなければならないのかと。
そして一方、こことは全く関係のない場所で、件の「騙り投稿」と全く同じURLを紹介して私を目の仇にしている人間がひとり存在します。
それがこれ↓
2chのSF・ファンタジー・ホラー板 山本弘 part20
http://megalodon.jp/2011-1207-1754-06/kamome.2ch.net/test/read.cgi/sf/1302740022/761-794
> 761 名前:名無しは無慈悲な夜の女王[] 投稿日:2011/10/26(水) 21:47:15.09
> どうでもいいことだけど、
> よしながふみの大奥の評論読んで、
> 冒険風ライダーは本当に数字に弱いことを、
> 実感したよ。
>
> 764 名前:名無しは無慈悲な夜の女王[] 投稿日:2011/10/27(木) 02:27:27.06
> >>762>>763へ
> ttp://www.tanautsu.net/blog/archives/weblog-entry-293.html
> ごめん、反省している。
> 山本弘のアンチサイト運営している冒険風ライダーって奴がかいたんだけど、
> こいつの論理は本当にイライラする。
> まあ、誤爆だったかもしれない。
「最新ではない記事」のURL紹介箇所が全く同じという時点で、まずはこいつが疑わしいと考えるべきでしょう。
さらに投稿を追っていくと、笑うべきことに自分の正体を暴露するような情報を吐露している箇所まであったりします↓
> 768 名前:名無しは無慈悲な夜の女王[] 投稿日:2011/10/28(金) 00:32:21.69
> >>766
> 嵐かどうか知らないけど、
> TPOをわきまえず山本弘の批判したり、
> 間違いを指摘されても認めず反論したり。
> >>765
> ttp://www.tanautsu.net/kousatsu02_03_aa.html
> 僕もそう思います。
> この件で、彼に恨みがあって、なかなか忘れられなかったり。
> 770 名前:名無しは無慈悲な夜の女王[] 投稿日:2011/10/28(金) 19:18:14.00
> >>769
> そうですね。
> でも、違うHNを名乗っていましたよ。
> まあ、自分でも子供じみたことだと思います。
> というか、古典SFファンさんが説得出来なかった時点で
> 諦めるべきだった。
自分が移動要塞論争に、それも私と対立する形で関わり、かつそのことで恨みを抱いている、などと自分から告白してどうするというのでしょうか、名無しがデフォルトであるはずの2chで(笑)。
移動要塞論争は何かと掲示板が荒れる紛糾のネタではありましたが、こんな後先考えない犯罪同様の手法でもって恨みを晴らそうなどと愚かしいことを考えるような理性の欠片も見出せない桁外れのバカなんて、あの論争に関わった誰かに該当なんてするのかねぇ、と私としてはつくづく考えずにはいられないのですけどねぇ(核爆)。