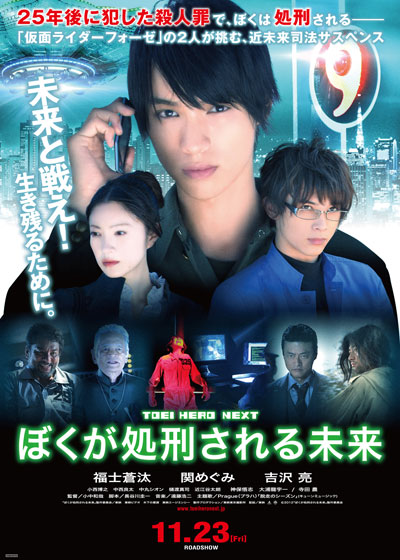第46回衆議院選挙が本日公示&選挙戦スタート
2012年の第46回衆議院選挙がついに公示され、本格的な選挙戦が始まりました。
日本憲政史上最悪のバカとキチガイの売国寄せ集め集団である民主党政権に終止符を打つ、日本国民にとって大変重要な選挙となります。
誰に、どの政党に投票するのかは地域によって、また人の数だけ異なるでしょう。
そんな有権者が最大公約数的にまずさし当たって始めるべきは、自分が属する選挙区の候補者の名と顔と所属を知るところからですね。
非常に簡単かつ当たり前のようでいて、実は意外にもこれが出来ていなかったりする人は多いのではないでしょうか。
かく言う私自身、選挙で候補者の名前と顔を知るのは投票直前の投票会場で、というケースが結構あったりします(T_T)。
私の場合、基本的には候補者ではなく政党で政治家を選ぶので、候補者について知る必要があまりなかったというのもあるのですが。
とにかく自民の候補者を選ぶとか、民主党と社民党と共産党は絶対に選ばないとか、個人的にはそれだけで充分だったりしましたからねぇ(^^;;)。
2009年8月の衆院選で小選挙区・比例代表共に自民党および自民党候補者に投票した際も、基本的にはそれで選んでいたりしていたのですし。
政党の候補者は、どんなに個人的な公約を掲げたところで所詮は政党の意向に拘束されざるをえないので、「それならば候補者ではなく政党をメインにして選んだ方が良いではないか」というのが私の考えでした。
それでも、時の「空気」に従うかのごとく民主党に投票して自身の選択を悔いる羽目になった他の有権者達に比べればこれでもはるかにマトモな判断になったというのは、何とも皮肉な話ではあるのですが。
ただまあ、候補者を全く見ることなく政党のみで選ぶというのも少々寂しいものはあったりするので、今回私の地元熊本の選挙区で出馬を表明している候補者達の名前を並べてみたいと思います。
熊本は県内に5つの選挙区があり、各選挙区の立候補者達はそれぞれ以下のようになっています↓
熊本1区
・山部洋史(46) 共産 新
・松野頼久(52) 維新 前
・池崎一郎(60) 民主 新
・木原 稔(43) 自民 元
・倉田千代喜(62)無所属 新
熊本2区
・福嶋健一郎(46)未来 前
・濱田大造(42) 民主 新
・本田顕子(41) みんな 新
・松山邦夫(59) 共産 新
・野田 毅(71) 自民 前
熊本3区
・本田浩一(45) 維新 新
・森本康仁(34) 民主 新
・坂本哲志(62) 自民 前
・東奈津子(43) 共産 新
熊本4区
・矢上雅義(52) 無所属 元
・蓑田庸子(61) 共産 新
・園田博之(70) 維新 前
熊本5区
・中島隆利(69) 社民 前
・橋田芳昭(57) 共産 新
・金子恭之(51) 自民 前
この中で一番注目されるべき戦いは、やはり何と言っても熊本1区でしょうね。
熊本1区は、松野頼久が過去の選挙で4回連続当選を果たしているのですが、当時の松野頼久が所属していた政党は一貫して民主党でした。
ところが今回、松野頼久は日本維新の会に鞍替えした上で選挙戦に臨んでおり、所属政党の変更が選挙にどのような影響を与えるのかが焦点となるでしょう。
個人的には、民主党はもちろん日本維新の会もまるで信用できませんし、ただ単に「選挙に勝つために党を鞍替えした」だけにしか見えない松野頼久自身にもどれほどの信頼性があるのか、はなはだ疑問ではあるのですが。
「ちょっと待て、その無所属(または他の政党名)は民主かも」の標語のごとく、所属政党が変わっただけで中身は全く変化していないでしょうからねぇ。
如何に4回連続当選の実績があるとはいえ、長年民主党を続けてきたという前歴も、松野頼久には大きなマイナスとならざるをえず、今回は苦戦が予想されるところでしょう。
一方、その松野頼久の最有力な対抗馬となるのは、安倍晋三自民党総裁自ら応援演説に駆けつけた、 自民党候補の木原稔。
民主党の逆風で自民党に追い風が吹いていることを鑑みても、今回の熊本1区は実質的に松野頼久と木原稔の一騎打ちになるのではないかと考えられます。
逆に笑うしかないのは熊本5区ですね。
これまた4選連続当選の実績を持つ金子恭之の対抗馬が、よりによって社民党と共産党の候補者しかいないって……。
無所属と日本維新の会の候補者による一騎打ちとなる熊本4区よりもはるかに一方的な勝負になるのが、最初から目に見えているではありませんか。
選挙前から既に勝敗は決しているとしか言いようのない選挙区ですね、熊本5区は(笑)。
こんな選挙区があるのを鑑みると、何かと弊害が指摘される比例代表の並立制度も、それなりに意義はあるのかなぁとついつい考えてしまいますね。
第46回衆議院選挙の投票日は2012年12月16日。
果たして、どのような国民の審判が、各政党および候補者達に下されることになるのでしょうか?